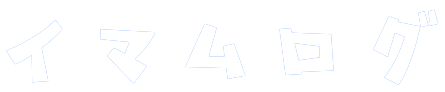「統計検定2級 合格」とかで検索すると、合格体験記がたくさん出てきて僕も参考にしながら学習を進めていました。
受ける人によってスタート地点は異なるので、たくさんある合格者の情報の中から自分のスタート地点にあった情報を探すのは少し骨が折れます。
統計検定の場合はどちらかというと「大学でも数学をやっている(やっていた)」や「現役でデータを扱う仕事をしている」というような分類の人が多い印象で、合格体験記もスタートから違うなぁ。。。と感じることが多かったです。(あくまで僕調べです)
僕の場合はそうではない分類に入るので、そのような人たちが統計検定2級の挑戦をする場合に少しでもお役に立てるといいなと思いこのブログを書こうと思いました。
あとXのポストから何人かが興味を持ってくださったのも励みになってます。ありがとうございます。
僕について
・大卒。偏差値は50くらい。建築について学んでいて一応理系だったが、数学は大学で履修してない
・数学は得意とは言えないが、苦手意識はない。至って並の成績だった
・学習開始時の高校数学の知識はほぼ忘れている状況
・統計やデータを扱う職種ではない
・統計検定2級の学習時は育休中
・初回の受検では不合格、2回目を1ヶ月後にして合格
統計検定2級合格にむけた学習
合格までの期間としては4ヶ月ほどかかったと思います。勉強時間は1日1〜2時間程度で、30分くらいのときもありましたがほぼ毎日勉強していたと思います。
・1〜2ヶ月はインプット。高校数学からやり直しました。(詳細は後述します)
・3〜4ヶ月で過去問演習とインプットを繰り返しました
インプットをじっくりめにやっていたと思います。反省点としては過去問にはもっと早く目を通しておくべきだったと思います。早めに過去問に対する理解ができていればインプットはもっとコンパクトにできていたかもしれません。
学習に使った教材
前述の通り、僕は高校数学からやり直す必要があったのでとても優しい教材を選び、まずは勉強を続ける意識付けを重視しました。教材は以下のものです。
マセマ出版社の教材で、極めて優しく学習できる教材だと思いました。本当に初学者向けなので少しでも分かる人には物足りないかもなレベルです。
僕自身はこの教材のおかげで勉強する習慣が身につきました。
統計検定2級に必要な内容としては数Ⅱの場合、微分積分。特に簡単な積分計算を押さえておけば十分です。
加えて積分とはなにか?を簡単にでも理解しておけば、統計学における確率とはどういうことなのか?という理解も捗ります。
数Aの場合、場合の数と確率です。一通り教材の内容を学習すれば十分で、特に条件付き確率はしっかり押さえておきましょう。統計検定2級においてはベイズの定理というものを使った確率計算が頻出のため条件付き確率の理解は必須になります。
教材を利用したのは以上です。
高校数学をおさらいしたところで、ようやく統計学の学習に入ります。教材は使用せず、Webサイトで学習をしました。以下2点をご紹介します。
鉄板中の鉄板かもしれないです。統計学を勉強し始めた人はだいたい見てるのでは?と思います。
Step 0〜2までありますが、統計検定2級に必要なのはStep 0と1で十分です。説明が簡素で少し分かりづらい箇所もあるかもしれませんが、網羅性は申し分ないです。特にStep 1は繰り返し読み進めて練習問題も解いて理解も深めることができれば、ある程度の得点(合格も可能かも?)は期待できそうです。
ちなみにStep 0の初級編はネコちゃんたちが小学校で過ごすストーリーになっていて学びながら癒やされました笑
こちらも知名度は非常に高いと思います。Youtubeも出されており解説がわかりやすいですが、特にブログのほうを推したいです。
統計WEBで疑問に思った内容をとけたろうさんがわかりやすく紐解いてくれるイメージです。僕としては1回目不合格時に酷かった推定や検定の理解がとけたろうさんのブログで一気に理解が深まりました。
インプットとしては以上です。
過去問演習についてはおなじみの「統計検定2級 公式問題集」です。
日本統計学会公式認定 統計検定 2級 公式問題集[2014〜2015年]
リンクは2014〜2015年ですが、僕は2011〜2013年、2016〜2017年、2018〜2021年、CBT対応版を購入し、2021年の問題を除いてすべて2周しました。
個人的に過去問は難易度にかなりばらつきがあるなと感じており、2級合格という意味での優先度としては2011〜2013年、2014〜2015年をまずは解いておくと良い気がします。基礎的な問題がまんべんなく出てきます。それ以降の過去問はやや難易度が高めかな?という感じがしたので、より実践的に理解を深めたい方はぜひ解いてみてください。
2021年については、どうやら難易度が高すぎるみたいで統計検定2級合格に向けてはわざわざ解く必要はないようです。実際に僕もノータッチで合格しました。準一級の学習に向けてはきちんと解いておこうとは思います。
セクション別の押さえるポイント
試験の内容自体を明かすことはできないので、過去問を一通り解いた上でここは頻出だよな〜というポイントを記載していきます。
前提として、幅広い範囲の中からランダムに基礎的な問題が35問程度出題される試験なので、これから記載するポイントだけを押さえるのではなくきちんと全範囲を押さえることを強くおすすめします。
統計検定2級は大きく3つのセクションに分かれていますので、各セクションごとに頻出(であろう)内容を記載します。
1、1変数・2変数記述統計の分野
箱ひげ図を中心としたデータの読み取り、散布図や相関係数は頻出かなと思います。
また、正誤問題もポツポツと出てくるので平均値や中央値、分散や標準偏差等、基礎的な言葉の意味を正確に理解しておく必要もあります
2、データ収集・確率・分布の分野
確率はベイズの定理は確実に押さえておきましょう。
確率変数に関しては期待値を求める簡単な積分計算、分布に関しては二項分布やポアソン分布の特徴(期待値と分散)を確実に押さえておきたいところです。
3、推定・検定・線形モデルの分野
推定は区間推定(母平均や母比率)。丸暗記はしんどいのできちんとプロセスを理解しておくことをおすすめします。
仮説検定は t 検定のなかでも2標本で対応のある場合とない場合や適合度検定、第一種の過誤と第二種の過誤を正確に理解したほうがいいです。
回帰分析については単回帰も重回帰も理解したうえで、よく問われるのは決定係数に関する内容かなと思います。ざっくりしてますが、見るべきポイントはシンプルであるケースがちょこちょこあります。
一元配置分散分析についてはいろんな言葉がでてきます。平方和、自由度、平均平方、水準、残差、F値等、それぞれの言葉の意味を正確に理解したら計算自体は簡単な内容です。
統計検定について
めっちゃいまさらな内容をここで記します。
これまでよくわからない内容を記載しましたが、統計検定2級はCBT方式の試験ですので画面の前で選択肢から正解を選ぶ方式の試験です。
しかも1画面に1問というケースが大半なので、選択肢の内容としては公式の微妙な違いの中から正解を選ばせたりするものも多いです。つまり、計算力はそこまで求められないものになってます。ありがたい試験ですね。
一方で試験時間は90分となっているので、意外とタイトです。なので問題文を読んで素直に計算するというよりは、問題文を読んでまずは選択肢をざっと見て半分くらいは削った上で計算コストを下げながら省エネで解答することをおすすめします。せっかく計算したけど選択肢を見て求められてない内容だった…というのもたまにありますので、意外と気をつけておくべきポイントだったりします。
あと、時間の話に関してもう一つ重要なことは問題を見てすぐに解答の方針が立てられないなら、その問題は飛ばす勇気を持ちましょう。あとから見返せるようにもなってますので1問に時間を取られすぎるのは、その後の焦りに繋がりますので要注意です。
さいごに
ざっと僕が統計検定2級に合格するまでのプロセスを記載しました。
以前のブログ(統計検定2級を受検したきっかけ)で記載しているのですが、そもそもは軽いノリみたいなもんで勉強して受検した統計2級ですが、実はとても身近な学問で理解を深めれば深めるほどハマっていってます。いつかは仕事でも活かしていきたいなと思います。準一級もがんばって合格をめざすぞ。
これから受けようと思っている人や興味のある人に少しでも多くこのブログが届くと嬉しいです。